介護業界でのキャリア形成ってどうなるの?
2020/01/09

介護業界で長く働き続ける人が多く通ってきたキャリア形成にどのようなパターンがあるのかを解説します。
生涯現役!現場主義を貫き通す
利用者の方と日常を共にすることを一番に考え、自ら直接的に求められるケアが提供できること、利用者の喜ぶ顔が見られることにやりがいを感じているといった場合は、先々まで現場における介護を軸にキャリアアップを考えていきたいというケースがあります。全くの無資格からスタートした場合は、短期的に取得できる資格として介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー資格)があります。施設によっては、資格取得を後押しする制度を整えている所もありますので是非活用しましょう。
また、その上位資格として介護福祉士があり、従来であれば現場での実務経験を3年積むことにより受験資格を付与されていた内容でしたが、2017年からの改定では介護福祉士実務者研修終了が受験条件となりました。こちらの資格取得を目指す場合は、事前によく受験概要を確認しておきましょう。
介護福祉士資格取得後も、さらに現場での経験を積むことで現場リーダー等になることもあるといえます。他の介護職員を取りまとめ、まだ経験の浅い介護職員の良きアドバイザーとなることで施設全体の介護スキルの向上、さらには利用者にとってより安心安全な介護を提供する担い手となることが期待されますといえます。
介護支援専門員を目指したキャリア形成
介護福祉士等の資格取得者は、実務経験5年以上で介護支援専門員試験を受験することが可能になります。2018年からは、従来の受験資格である実務経験の内容がより限定的となりましたので受験希望者は注意が事前によく確認する必要があるといえます。介護支援専門員の合格率は平成27年度で約15%となり、難易度の高い資格といえます。
その分、給与条件において基本給や資格手当のベースアップも期待できる上、資格取得者でなければできない業務をおこなうこともできます。ただ、各施設における介護支援専門員の人数はあまり多くないケースが多く、資格取得ができたからと言って必ずしも希望する職場へと早々に配置転換されるわけでもないというのが現状のようです。そのため、この場合は、介護支援専門員として採用してくれる職場へ資格取得を機に転職する人も少なくありません。
介護支援専門員として採用された場合、業務内容として直接的な介護業務からは多くの場合離れることになります。介護業界の離職理由として多く挙げられる腰痛等の身体的負担は少なくなり、長期にわたって先々まで仕事を継続しやすくなることもメリットといえるのではないでしょうか。
相談援助業務を目指したキャリア形成
利用者や家族からの相談役としての仕事を希望する場合、現場の介護経験を積んだとしても、それだけでは、なかなか機会が回ってくることはありません。多くの場合、相談員として活躍するためには社会福祉士や精神保健福祉士等の国家資格が必要となってきます。福祉系4年生大学を卒業する他、専門の短大や専門学校卒業に加えて相談援助実務経験1~2年、あるいは実務経験4年に加えて社会福祉士一般養成施設1年などいくつかのパターンで受験資格を得ることが可能となっています。
受験資格取得に至るまでで必要科目の履修が必須であるため、通学あるいは通信での教育カリキュラム受講を欠かすことができず、一度社会人となってから目指す資格としては計画的に時間をかけて取得を目指すものと考えましょう。それでも、現場で働きながら通信教育やスクーリングに通うことで資格取得を果たした方も多いですから、しっかりと勉強して目指してみる手もあります。
管理・運営者を目指したキャリア形成
福祉業界では現場経験を積むことにより、施設長など管理職へ就く場合があります。施設長など管理職に登用される人数は基本的に各施設1人となります。すでにそのポジションが埋まっている場合は、いくら自分の経験値が上がっていても回ってくる可能性が低いとも考えられます。
その場合は、介護支援専門員資格を取得し、自分でグループホームや居宅介護事業所などを立ち上げる方も少なくありません。自分の理想とする施設を自ら作りたいと考える方は、介護支援専門員の資格取得を目指して損はないのではないといえます。
おすすめの記事
-
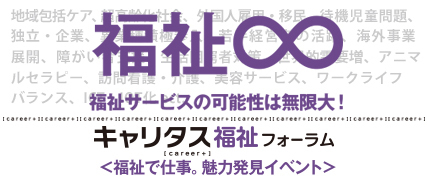
▼福祉フォーラム開催日程
詳しくはこちら
少しでも福祉に興味を持ったら参加! -

待機児童問題の最前線
詳しくはこちら -

ソーシャルビジネスのグローバル化
詳しくはこちら -

海外の高齢化の現状
詳しくはこちら



